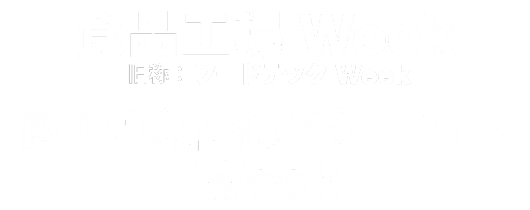居酒屋の経営は難しい?開業の方法や手順、成功のポイントなどを詳しく解説
居酒屋を含む飲食店は、開業率が高い一方で廃業率も高く、競争が激しい業界です。開業・経営を検討しているなら、事前の情報収集や準備を行いましょう。
本記事では、居酒屋の経営方法や開業までの流れ、必要な資格・届出などを紹介します。居酒屋の経営が難しいとされる理由や、成功させるための重要なポイントも紹介するため、居酒屋の経営に携わる予定のある方は参考にしてください。
居酒屋の開業・経営の方法
居酒屋の開業・経営の方法は大きく2つに分けられます。
- 個人で開業・経営する
- フランチャイズで開業・経営する
以下でそれぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく紹介します。
個人で開業・経営する
個人で居酒屋を開業・経営する場合、自分自身のビジョンやこだわりを反映できる点が大きな魅力です。例えば、独自のメニューや店舗のデザイン、接客スタイルを自由に決めることができ、オリジナリティの追求が可能です。
フランチャイズ料やロイヤリティを支払う必要がないため、初期投資や運営費用を抑えられる点もメリットです。
一方、集客や広告戦略、運営ノウハウは自分自身の能力に依存するため、経営やマーケティングに関する知識や経験が必要になります。
フランチャイズで開業・経営する
フランチャイズで居酒屋を開業する場合、既存のブランドやノウハウを活用できます。マニュアルを提供してもらえたり、支援を受けられたりするため、未経験者でも経営をはじめやすいでしょう。
マーケティングや仕入れ先、スタッフ教育などのサポートが充実しているケースもあり、安心して経営・開業しやすい点がメリットです。また、ブランドの認知度や集客力を活用できるため、個人ではじめるより集客に困ることが少なく、安定した集客が期待できます。
一方、売上の一部をフランチャイズ料やロイヤリティとして支払う必要があり、利益率に影響する可能性があります。店舗の運営方法やメニューに関してもブランドの方針に従う必要があり、個人経営と比較すると自由度が低くなる点はデメリットになるでしょう。
また、同じブランドで食品事故や企業トラブルなどが起きた際は影響を受けるため、ブランドに依存する分リスクもあります。
居酒屋を開業して経営をはじめるまでの流れ
居酒屋や飲食店の経営をはじめるまでの一連の流れは以下のとおりです。
- 開業の動機やビジョンを明確にして準備する
- コンセプトやターゲット層を明確にする
- 事業計画書を作成する
- 資金調達を行う
- 物件探しや設備の準備を行う
- 内装工事を開始する
- 必要な資格の取得や届出をする
- スタッフの採用・研修・教育を行う
- 集客・販促を行う
- メニューの考案や仕入れをする
- オープンする
それぞれ詳しく紹介します。
開業の動機やビジョンを明確にして準備する
居酒屋を経営して成功させるためには多角的な視点が必要です。まず、居酒屋を開業するにあたり、動機やビジョンを明確にしましょう。
大前提として、居酒屋を運営するには、仕入れや接客など幅広い知識やスキルが求められます。飲食業の経験があれば、どんな経験が活かせるのかを考え、必要に応じてさらに知識やスキルを身につけましょう。さらに、自分の強みをどう運営に活かすことができるのかも考えましょう。例えば、SNSが得意ならSNSを活用したプロモーションを行うことが挙げられます。
また、この段階で資金や人材、仕入れ先などの確保を進め、スムーズな開業前と安定した経営に繋げられるよう準備することが大切です。
飲食店の経営には、長時間労働やリスクも伴います。事前に家族や大切な方々と相談し、支援体制を整えた上で、安心して開業できる環境を整えましょう。
コンセプトやターゲット層を明確にする
店舗のコンセプト設計やターゲット層の選定は、開業前の重要なステップです。居酒屋は競合が多いため、差別化できないと集客に苦労し、安定した経営が難しくなるおそれがあります。
「炭火」「囲炉裏」「藁焼き」をはじめとする調理方法や、「発酵調味料」「ジビエ」「希少日本酒」の調味料や素材、酒などで差別化を図り、店の雰囲気や提供する料理、サービスの特徴を明確にすることが大切です。
ターゲット層がインバウンド層なのか、アクティブシニア層なのかによっても、メニューや価格設定、店舗の内装や出店する場所の立地などが変わります。ターゲット層を明確にすることで、マーケティング戦略や集客方法も決まりやすくなるでしょう。また、コンセプトやターゲット層を明確にすると、開業後に迷いが生じても立ち戻って方向性を再確認できます。
事業計画書を作成する
事業計画書を作成し、開業後の目標や戦略を明確にします。市場調査を基にターゲット層や競合の分析を行い、店舗運営の基本方針を作成しましょう。
売上予測や経費計画、資金繰りの見通しを立て、現実的に収益が上がるかどうか検証することが重要です。事業計画書は融資を受ける際に必要です。資金調達前に作成しておきましょう。
資金調達を行う
飲食店の開業には、設備投資や初期費用が多くかかるため、自己資金だけで賄えない場合は状況に応じて資金調達が必要です。銀行や投資家から融資を集める方法の他、特定の条件を満たせば助成金を活用できる場合もあります。
近年では、クラウドファンディングで資金調達する方法もあり、うまく活用できれば広告効果も期待できます。
いずれかの方法を活用して融資を受けるためには、事業計画書を作成し、計画の実現可能性を示すことが重要です。現実的な資金計画を整えるために、内装工事業者や厨房機器メーカーから概算見積もりを取りましょう。
融資額や返済計画を明確にし、収益性を証明すると、より融資を受けやすくなるでしょう。
飲食店で活用できる助成金・補助金についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
物件探しや設備の準備を行う
物件選びも居酒屋経営で重要なポイントのひとつです。立地は集客に大きく影響するため、ターゲット層に合った場所を選びましょう。物件の広さや賃料、必要設備の設置・稼働の可否、インフラ(電気・ガス・給排水・給換気など)の整備状況、周辺環境の確認が必要なポイントです。
特に賃料は一番重要なポイントです。事業計画書で算出した賃料設定を守りましょう。なお、飲食店を出店できない地域もあるため、十分に下調べをしておくことが大切です。
物件の決定後は店舗の設備を整える必要があります。厨房機器や食器、冷暖房設備など、営業に必要なものを揃えましょう。
設備の選定は、経営の維持にも影響します。機能性や耐久性、メンテナンスのしやすさを考慮し、経営や予算に大きな影響が出ないようにすることが重要です。
内装工事を開始する
内装工事は店舗の雰囲気を決定付ける部分です。コンセプトに合ったデザインを選び、店舗のイメージにあわせて仕上げましょう。
内装工事を進める際には、店舗のレイアウトや動線にも注意を払い、スタッフが働きやすい環境を作ることを意識します。売上に対する適正な人件費に合わせてオペレーションを整えることが重要です。工事が完了した後は工事計画書と照らし合わせて、全体や細かい部分まで確認しましょう。
必要な資格の取得や届出をする
飲食店を開業する際には、必要な資格や許可を取得し、所定の届出を出す必要があります。食品を取り扱う店舗で必要な代表的な資格は「食品衛生責任者」です。
居酒屋の場合、「食品衛生責任者」と「防火管理者」の設置、「営業許可」の申請が多くのケースで必要となります。
店舗の規模や営業形態に応じて必要な資格や各種届出が異なるため、事前に確認して滞りなく準備を進めましょう。必要な資格や届出の種類は後述します。
スタッフの採用・研修・教育を行う
スタッフを採用する場合、必要な人数や役割を明確にし、研修・教育の手順まで考えておくことが大切です。スタッフの接客スキルや厨房での作業スキルは顧客満足度に直結するため、居酒屋の経営を継続する上では欠かせません。
採用後の研修やルール、マニュアルの作成は、スタッフの質を安定させる方法として効果的です。開業前に作成し、開業後も適宜見直しをして修正・改善しましょう。
集客・販促を行う
開業前や開業直後の集客は売上に関わる重要なステップです。ターゲット層に向けた宣伝活動を行い、店舗の認知度向上を図ります。
SNSを活用して開店情報を発信したり、地元の広告媒体に掲載したりするなど、集客方法は様々です。近年では検索エンジンを活用して、主にGoogleマップ上に掲載する方法(MEO対策)もあります。
低コストからはじめられ、高い集客効果を見込める可能性もあるため、集客方法についても事前に調べておきましょう。
MEO対策についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
メニューの考案や仕入れをする
メニューはコンセプトやターゲット層にあわせて作成します。定番メニューを取り入れつつ、競合との差別化を図るメニューの考案も重要です。
メニューを考案する際には、食材の仕入れ先の選定やコスト管理を行いましょう。特に希少な食材やこだわりの特産品は事前に売手との商談が必要になるケースも少なくありません。
価格がターゲットに見合わなかったり、利益率が低くなったりすると、集客や経営の維持に影響を及ぼします。
低コストで提供できる魅力的なメニューの考案や、季節ごとのメニューや限定メニューの提供などで独自性を保ちましょう。
オープンする
準備が完了したらいよいよ店舗のグランドオープンです。その前に「プレスリリース」「レセプションパーティー」「招待客のみの内覧会」「プレオープン」「シークレットオープン」など、販促活動を行うことをおすすめします。
オープン後は、リピーターの獲得やサービス・品質の維持に努めましょう。
長期的な目線で評判を高め、居酒屋を経営していくことが大切です。
居酒屋を開業・経営する際に必要な資格・届出
居酒屋や飲食店の経営では、業態によって様々な資格や届出が必要になります。以下はその一例です。
- 食品衛生責任者
- 防火管理者
- その他の資格
- 飲食店営業許可
それぞれ詳しく紹介します。
食品衛生責任者
食品衛生責任者とは、HACCPに基づいて衛生管理にあたる人のことをさし、食品衛生法に基づき設置が義務付けられています。
特定の業種で設置が必要な「食品衛生管理者」とは異なり、食品衛生責任者の設置は全ての営業者が対象です。また、設置の届出は管轄の保健所に提出する必要があります。届出の提出は忘れずに行いましょう。
HACCPや食品衛生管理者についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
防火管理者
防火管理者は、居酒屋の規模に応じて取得が必要な資格です。飲食店は特定用途の防火対象物(不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある防火対象物)に区分されます。
収容人員が30人以上(従業員を含む)の場合は防火管理者の選任が必要です。該当する場合、管轄の消防署へ届出を出す必要があります。
その他の資格
居酒屋の経営で必要になる可能性があるその他の資格や届出は以下です。
酒類販売業免許は必須ではありませんが、デリバリーやテイクアウトが可能で、店舗の外で飲める状態で提供する場合(営業場所以外での飲酒が可能な場合)には取得が必要です。
店舗の業態やサービスの提供にあわせて、必要な資格の取得や届出の提出を行いましょう。
飲食店営業許可
飲食店営業許可は、飲食店を営業するために必要な届出です。食品関係の営業は調理業、製造業、処理業、販売業に分けられ、食品衛生法で定められた営業許可が必要です。居酒屋をはじめとする飲食店は「調理業」に分類されます。
営業許可の申請は管轄の保健所で行い、営業許可申請に伴って水質検査をはじめとする施設検査が行われます。管轄の保健所に事前相談する他、申請書類は施設工事完成予定日の10日前には提出しておきましょう。
居酒屋を開業・経営する際に必要な費用の相場と内訳
居酒屋をはじめとする飲食店を開業する際に必要な費用の相場は600〜1,000万円前後とされています。
2024年の日本政策金融公庫総合研究所のデータを参考にすると、開業時の資金調達額は平均1,197万円です※。実際にかかる費用は店舗の工事や導入設備にかかる費用などにより異なりますが、主な内訳は以下のとおりです。
- 物件取得費用
- 設計料・内装・外装工事費用
- 機械・什器・備品費用
- 運転資金(光熱費、人件費、家賃、材料費など)
予算を決めておくとともに、事前に見積もりを出しておきましょう。また、開業がゴールではないため、開店後に安定するまでの経営期間を含めた資金繰りが重要です。
居酒屋の経営における開業・廃業状況
居酒屋をはじめとする飲食店は開業率が高いですが、廃業率も高い業種です※。開業率は「当該年度に新規に成立した事業所数/前年度末の適用事業所数」、廃業率は「消滅した事業所数/前年度末の適用事業所数」で割り出します。
2024年の廃業率は前年に比べて約16%増加したとのデータもあり、飲食店のなかでも特に居酒屋を主体とする「酒場、ビヤホール」の廃業件数が多いです。
上記の傾向から居酒屋をはじめとする飲食店を経営する際には、事前の準備や情報収集、開業後の安定した経営が鍵となることがわかります。
居酒屋の経営が難しいとされる主な要因
居酒屋の経営が難しいとされる主な要因は以下です。
- 初期費用の負担が大きい
- 競合が多い
- 外的要因で売上が大きく変動しやすい
- 人手不足に陥りやすい
- 長時間労働になりやすい
- 利益率が低い
飲食業は入職率が高い反面、離職率が高い業種で、慢性的な人手不足に悩まされています。初期費用の大きさや競合の多さに加え、物価の変動に影響を受けやすい点も経営が安定しない理由です。
そのため、利益率やマーケティング方法などはよく考えて行うことが大切です。
飲食店経営についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
居酒屋の経営を成功させるために重要なポイント
居酒屋の経営を成功させるために、以下のポイントを押さえておきましょう。
- コンセプト設計を綿密に行う
- 市場調査や店舗周辺の環境をリサーチする
- 原価管理や利益率管理を徹底する
- QSCの向上を意識する
- 集客・販促の方法を工夫する
- 業務効率化に役立つシステム・ツールを導入する
それぞれ詳しく紹介します。
コンセプト設計を綿密に行う
居酒屋経営を成功させるためにはコンセプト設計が欠かせません。コンセプトはターゲット層やメニュー内容、価格、店舗の内装、出店場所、マーケティング手法など、様々な要素に影響します。
経営に迷った際やうまくいかない時も、コンセプトが明確なら、コンセプトに沿って修正が可能です。コンセプトをブラッシュアップすれば、競合との差別化が図れる他、リピーターの獲得にもつながりやすいでしょう。
市場調査や店舗周辺の環境をリサーチする
居酒屋を開業する前には、市場や店舗の立地環境のリサーチが重要です。周辺の競合店の価格帯や人気メニューを分析すると、差別化できる要素を発見できるかもしれません。
また、駅からの距離や曜日ごとの人の流れなども確認しましょう。予算の範囲に収まる立地でも、集客が見込めない場所だと経営を続けることが難しくなるケースがあるので、事前のリサーチは重要です。
原価管理や利益率管理を徹底する
居酒屋を経営する上では、売上だけでなく原価や利益率の管理も重要です。日本政策金融公庫は、小規模の飲食店を対象に調査を行っています。
2024年の調査によると、「酒場、ビヤホール」の売上高営業利益率は5.7%(黒字かつ自己資本プラスの企業の平均)でした。飲食店の目安は10〜15%とされているため、5.7%は高い数値ではありません。
居酒屋を経営するのであれば、まずは10%を超えることを目標に設定し、原価管理や利益率管理を行いましょう。
飲食店の利益率目安や計算方法についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
QSCの向上を意識する
居酒屋の成功には、QSCの向上が欠かせません。QSCとは、顧客満足度を向上させるための行動指針の頭文字をとった言葉です。
- Q(Quality):品質
- S(Service):サービス
- C(Cleanliness):清潔さ
QSCの導入や取り組みにより、以下のメリットが期待できます。
- 顧客ニーズの多様化への対応
- 売上向上と利益の安定化
- ブランドイメージ向上と他社との差別化
- クレーム・トラブルの軽減
- 従業員のモチベーション維持・向上
近年では、QSCに加え、H(おもてなし、Hospitality)、A(雰囲気、Atmosphere)、V(価値、Value)が付け加えられて活用されています。大手企業でも採用されており、実践することでサービスの質の改善に繋がります。
QSCについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
集客・販促の方法を工夫する
居酒屋の集客には、ターゲットに合った効果的な手段を選ぶことが大切です。近年ではSNSを活用した集客・販促の方法が特に重要で、うまく利用できれば低コストで高い広告効果が期待できます。
アナログな手法と併用すると、より幅広い層にアプローチできるでしょう。また、集客・販促活動は長期的な目線で取り組むことも大切です。
飲食店の集客方法についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
業務効率化に役立つシステム・ツールを導入する
居酒屋の経営に役立つシステムやツールの導入も検討しましょう。
例えば、POSレジシステムを導入すると、売上データの管理や分析が容易になり、売れ筋メニューの把握や在庫管理の最適化が可能になります。また、モバイルオーダーシステムを活用すると、注文ミスを減らし、ホールスタッフの負担を軽減できるでしょう。
その他、予約管理システムや配膳ロボットなど、実際に導入されているシステム・ツールは人件費削減や利益向上に役立っています。
飲食店の業務効率化ツールについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
居酒屋の経営に役立つ情報を収集するなら「レストランマネジメントEXPO」へ
居酒屋の開業や安定した経営を目指しているなら、ぜひ「レストランマネジメントEXPO」にご来場ください。
「レストランマネジメントEXPO」とは、飲食店の経営や店舗管理の課題を解決するサービス・情報が集まる展示会です。飲食店の経営や店舗管理の課題を解決するための、受発注システム、勤怠管理システム、採用・雇用支援、WEB・SNSマーケティング、炎上・防犯対策など各種サービスが一堂に出展します。
展示会では、製品・デモを体験できる他、飲食店経営のポイントや他社事例を紹介するセミナーを併催しており、経営のヒントを学ぶことが可能です。
さらに、POSシステムや配膳ロボットをはじめ、飲食店の人手不足解消や業務効率化を実現するデジタル技術が出展する「スマートレストランEXPO」も同時開催します。居酒屋の開業や経営に役立つ情報収集の場としてご活用ください。
展示会へは、事前登録をすれば無料で入場可能です。関連サービスや製品を扱う企業なら出展側としての参加も可能なため、自社製品の認知度向上の場や他社とつながる機会にもご活用いただけます。
具体的な商談の実現・リード案件獲得につながる可能性があるため、ぜひ出展側での参加もご検討ください。
■レストランマネジメントEXPO 2025
会期:2025年12月3日(水)〜5日(金)
会場:幕張メッセ
■スマートレストランEXPO 2025
会期:2025年12月3日(水)〜5日(金)
会場:幕張メッセ
居酒屋の経営には最新情報の収集と徹底した事前準備が重要
居酒屋は競合が多い業界のため、開業後に経営を安定させるためには徹底した事前準備が大切です。慢性的な人手不足にも悩まされている業界のため、業務効率化に役立つシステム・ツールの導入も視野に入れましょう。
開業前に最新のサービスや業界のトレンドに触れておくことも大切です。居酒屋の開業や経営を考えているなら、ぜひ「レストランマネジメントEXPO」にご来場ください。展示会では、業務効率化やマーケティング手法など、飲食店の経営に関する最新情報の収集が可能です。
■レストランマネジメントEXPO 2025
会期:2025年12月3日(水)~5日(金)
会場:幕張メッセ
■スマートレストランEXPO 2025
会期:2025年12月3日(水)~5日(金)
会場:幕張メッセ
▶監修:宮崎 政喜(みやざき まさき)
エムズファクトリー合同会社 代表 / 料理人兼フードコンサルタント
出身は岐阜県、10代続く農家のせがれとして生まれ、現在東京在住。プロの料理人であり食品加工のスペシャリスト。また中小企業への経営指導、食の専門家講師も務めるフードコンサルタントでもある。飲食店舗・加工施設の開業支援は200店舗以上。料理人としてはイタリアトスカーナ州2星店『ristorante DA CAINO』出身。昨今、市町村や各機関からの依頼にて道の駅やアンテナショップも数多く手掛ける。今まで開発してきた食品は1000品目を越え、商品企画、レシピ開発、製造指導、販路開拓まで支援を日々実施している。
▼この記事をSNSでシェアする