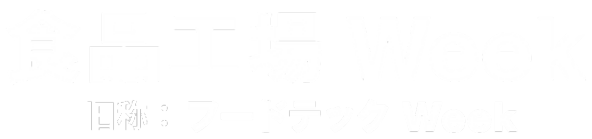食品製造業のDXとは?重要性や業界の課題・企業の導入事例を紹介
食品製造業界は、人手不足や品質管理の厳格化、低い生産性など多くの課題に直面しています。このような課題の解決には、DXの導入が不可欠です。
一方、DXの必要性は理解していても、具体的に何をすべきかが明確でない方も多いのではないでしょうか。
また、DXの推進は抜本的な改革につながるため、踏み出せないでいる企業も多いかもしれません。
本記事では、食品製造業におけるDXの重要性や業界が抱える具体的な課題、DXを活用している企業の事例を紹介します。食品製造業に携わり、DXの推進を考えている方はぜひ参考にしてください。
食品製造業のDXとは?
そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、ひとことでいうと「ITを活用し、ラクをして利益を生み出す 企業文化を再構築すること」です。
DXはDigital Transformationの略で、デジタル技術を活用して新たなサービスや商品の提供やビジネスモデルの開発を行い、産業内や組織文化の変革を促すことをさします。変革を意味するTransを欧米では「X」と省略する文化があるため、DTではなくDXと略されます。世界中で使われる用語ですが、厳密な定義は一致していません。
日本政府では以下の定義がなされています※。
「企業が外部エコシステム(顧客、市場)の劇的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること」
食品製造業もDXの推進が行われている業種のひとつです。食品製造業のDXは、ロボットやAI、IoTなどの最新技術によって食品製造業の課題を解決し、生産性の向上や生産管理に革新を起こすことを目的としています。
DXの定義や、食品業界のDXについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
DXとデジタル化の違い
「デジタル化」と混同されやすいDXですが、内容は大きく異なります。
デジタル化はデジタル技術を用いた産業の効率化や自動化であるのに対し、DXはデジタル技術で社会に根本的な変化をもたらし、新たな価値を創出することが目的です。
DXにとって、最新のデジタル技術を取り入れるのはあくまでも手段であり、目的ではありません。DXの本来の目的は、ビジネスモデルの変革や新たな価値の創造です。
食品製造業の課題とDX推進が必要な背景
食品製造業は様々な課題を抱えており、解決策としてDXの推進が重要視されています。食品製造業の主な課題は以下のとおりです。
- 国内マーケットの縮小
- 人手不足と低い労働生産性
- 食品ロスなどの社会問題への対応
- 高まる品質管理の水準
- 伝統や職人気質を重視する傾向
以降でそれぞれ詳しく紹介します。
国内マーケットの縮小
2021年の農業・食料関連産業の国内生産額は108.5兆円で、全経済活動の国内生産額の約11%を占めています。食品製造業だけに限定すると36.5兆円です※。
国内の市場規模は人口減少や高齢化に伴い縮小し、2020年から2050年までに20%減少すると見込まれています※。市場規模は縮小しているものの、健康志向や環境志向など消費者のニーズは多様化しており、企業側は柔軟に対応しなければなりません。
一方、世界全体でみると人口は増加しており、農産物マーケットは2020年から2050年にかけて30%拡大する見込みです※。日本の食品産業は、持続的な発展のためにグローバル市場への積極的な進出を見据えた経営や商品開発が必要とされています。
食品製造業を含めた食品関連業界は変化への対応が求められており、解決策のひとつとしてDXへの期待が高まっています。
人手不足と低い労働生産性
少子高齢化に伴う労働人口の減少も日本の食品製造業が抱える課題のひとつです。
食品関連事業者の社長は3〜5割程度が70歳以上で、事業継承を考えていない事業者の割合も半数以上を占めています※。労働人口は2017年比で2040年までに8%減(525万人減)が見込まれており、60歳以上の割合は20%から30%まで増加する見込みです※。
一般的に資本金が大きく、食品製造業の労働生産性は事業所規模が大きくなるほど拡大します。しかし、日本の食品製造業は従業員100人未満の事業所が全体の9割を占めている状況です。
経済産業省「企業活動基本調査(2021)」によると、以下のとおり、労働生産性は全産業の平均や同業種と比較しても高くありません※1。労働生産性※2に加え、経常利益率や賃金も全産業平均や同業種と比較して低い状況です。
食品産業の生産性の低さを解決するため、ロボットやAI、IoTなどを活用した食品の製造・品質管理などの自動化、リモート化が推進されています。
※1出典:農林水産省「食品産業の生産性向上・事業承継について」
※2労働生産性とは、パートタイマー等を含む従業員数で付加価値額を割った割合であり、雇用形態や労働時間は考慮していません。
食品ロスなどの社会問題への対応
食品ロスは持続可能な開発目標(SDGs)のターゲットであり、世界的に削減目標が定められている社会問題のひとつです。令和4年度の日本の食品ロスは約472万トン、事業系・家庭系食品ロスそれぞれで236万トン発生しています※1。
日本では、食品リサイクル法の基本方針で「事業系食品ロスの削減に関して、2000年度比で2030年度までに半減させる」との目標が立てられており※2、都道府県や市町村には食品ロス削減推進計画の策定(努力義務)も求められています。
食品製造業で発生する食品ロスの主な要因は、納品期限切れや売れ残りなどです。食品ロスを減らすためには、賞味期限の延長・年月表示化、過剰生産の削減などの対応が必要でしょう。
DXを推進し、AIを用いた需要予測が可能になれば、食品ロスの削減にもつながるとして期待されています。
食品ロスの現状や問題点については以下の記事で紹介しています。
高まる品質管理の水準
様々な課題を抱える食品製造業ですが、求められる品質管理の水準は高まっています。令和3年6月から、原則全ての食品等事業者はHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が求められるようになりました。
微生物による汚染、金属の混入などがないよう、継続的に監視・記録し、問題のある製品の出荷を未然に防ぎ、食の安全性を高めなければなりません。
複雑化する品質管理を効率化、自動化する手段としてAIやIoT技術の活用が期待されています。
HACCP(ハサップ)については以下の記事で詳しく紹介しているため、ぜひあわせてご覧ください。
伝統や職人気質を重視する傾向
食品業界は、長年にわたり築かれた伝統や職人気質が重要視されることが多い業界です。職人の匙加減、過去の成功事例、修行経験などを美化する傾向があります。これらはひとつの文化ですが、一方で、新しい技術やデジタル化が導入されにくいという側面があります。
食品製造業でDXが進まない主な理由
食品製造業に関わらず、日本はDX推進が遅れている国のひとつです。経済産業省の調査によると、2022年の日本のデジタル競争力は63カ国中29位、うち人材は50位、デジタル・技術スキルは62位と低い状況です※1。DX人材不足を感じている日本の企業は76%で、アメリカの43%と比べても高いことがわかります。
各国の企業約3,000社への調査では「デジタル化を進める上での課題・障壁」に対する回答に、以下の内容が挙げられています※1。
日本では、人材不足やデジタル技術の知識・リテラシー不足、アナログな文化・価値観の定着などが主な課題・障壁に挙げられています。一方、「デジタル人材が不足する理由」に関する回答は以下のとおりです※1。
「デジタル人材を採用する体制が整っていない」や「デジタル人材を育成する体制が整っていない」との回答が多く、現状の課題であるとわかります。
独立行政法人中小企業基盤整備機構の調査では、DXの必要性は約7割以上の企業が感じていると答えています。その反面、実際に取り組んでいる企業や取り組みを検討している企業は約3割程度です※2。
調査結果から、必要性は理解しているものの、人材や予算の確保が難しいことが食品製造業でDXが進まない主な原因として考えられるでしょう。
食品製造業でDXを推進するメリット
日本ではDXが遅れているものの、DXを推進した企業では約8割の企業がDXの効果を感じていると回答しています※。DX推進による主なメリットは以下のとおりです。
- 効率化・自動化による人手不足の解消
- デジタル技術の導入による人的ミスの削減
- サプライチェーンを含めた一貫管理ができる
- 適切な在庫管理による食品ロス削減
効率化・自動化による人手不足の解消
DX推進により、AIやIoT、ロボット技術を導入すると業務の効率化・自動化が進み、品質管理や在庫管理などの人的リソースを削減できます。業務の効率化や自動化は、人手不足に伴う課題の解消につながるでしょう。
また、人件費の削減、労働時間の短縮、従業員の負担軽減も期待できます。
デジタル技術の導入による人的ミスの削減
デジタル技術の導入により、AIやロボットが作業を代行すると発注ミスや工程ミスなどの人的ミスを防げます。人的ミスが削減できれば生産性の向上が期待できるでしょう。
異物混入検査など精密な作業は機械の方が得意な場合も多く、検査の精度が向上して品質の改善にもつながります。
サプライチェーンを含めた一貫管理ができる
DX推進により、サプライチェーンを含む製造過程の一貫管理も可能になります。一貫管理では、原料調達から顧客への提供までの全工程の管理が可能です。
AIやIoT、ロボットを導入するとデータの収集・分析が進み、業務全体の「見える化」も実現します。不透明だった部分が明確になり、改善や最適化をしやすくなるでしょう。管理がデータ化されると、業務負担も軽減されます。
適切な在庫管理による食品ロス削減
DXの導入によって一貫管理が可能になると、適切な在庫管理ができます。原料調達から販売までの各段階での在庫状況がリアルタイムで把握でき、効率的な在庫管理が可能になるためです。前述のとおり、蓄積されたデータをAIで分析すれば、精度の高い需要予測が立てられ、生産・販売・在庫の調整がよりスムーズに行えます。
結果的に過剰な在庫を抱えるリスクが減り、過剰在庫の廃棄で問題になっている食品ロスの削減にもつながります。
DX推進で課題を解決した食品製造企業の事例
DX推進で課題を解決した食品製造企業の事例をいくつか紹介します。
- Wi-Fiで生産過程の課題を克服した事例
- IoTで食品の品質管理を効率化した事例
- AI、IoTによりスマートファクトリー化した事例
DX推進を考えている方は参考にしてください。
Wi-Fiで生産過程の課題を克服した事例
まずはWi-Fi環境を整備して生産管理システムの課題を克服した企業の事例です。
もともと自動化を進めていたお菓子の生産工場では、Excelを用いた販売・生産管理システムを導入し、一元管理していました。しかし、生産計画の確認や生産数量の入力のため、事務室と工場との往来が必要で、Excelベースの在庫・出庫管理が原因のミスが多発したようです。
そこで、Wi-Fi環境を整備し、今まで事務室でしか閲覧できなかった生産管理システムを生産ライン内で利用できるようにしました。タブレットやバーコードスキャナーを使った出荷検品システムを導入した結果、作業効率の改善や人的ミスの削減に成功しています。
IoTで食品の品質管理を効率化した事例
次は、非効率だった作業をIoTの導入により効率化した事例です。
鰹のなまり節を製造していた企業は、燻す工程の温度管理を目視で行っており、温度異常による事故管理の手間や、焦げによる食品ロス発生が課題でした。
そこで課題解決のために導入したのは、IoT(モノをインターネットにつなぐ技術)です。設置した温度センサーにより温度分布を24時間計測可能にし、誰がどこからでも温度を確認できるようクラウド化も進めました。
異常の確認がしやすくなった結果、早急な対応が可能になり、食品ロスの削減や火災発生防止などの安全対策強化に成功しています。
AI、IoTによりスマートファクトリー化した事例
最後にご紹介するのは、AIやIoT技術の導入によりスマートファクトリー化した企業の事例です。
工場内で生産ラインのトラブルやエラーを把握し、生産の効率化の方法を試行錯誤していた企業ですが、運用による業務負担の増加との課題に直面していました。
近年になりAIやIoT技術が発展し、導入してスマートファクトリー化を進めています。スマートファクトリー化により、作業効率の向上や生産プロセスの最適化、人為的ミスの減少が実現されています。
リアルタイムで収集したデータを活用した迅速な意思決定や予防保全が、生産性の向上とコスト削減につながった事例です。
DX推進にはLTVの可視化もおすすめ
DXを進める際、LTV(ライフタイムバリュー)の可視化をするのは良い戦略です。LTVとは、「顧客生涯価値」の意味で、ある顧客が自社と取引を開始してから終了までの期間にどれくらいの利益をもたらしてくれたかを示すものです。
DXを推進すると、LTVの向上が期待できます。DXで顧客行動や購買履歴、嗜好データなどをより正確に分析し、顧客のリピート率や購入単価の向上を図り、劇的に変化する顧客ニーズを把握することで、テストマーケティングをしなくても、仮説検証の精度が向上します。
大量生産大量消費ではなく、多品種少量生産や、個性的消費にも順応できるということです。
食品製造業のDXに関わる情報収集・製品比較なら「フードテックジャパン」へ
食品製造業向けDXソリューションの導入検討、最新技術の情報収集なら「フードテックジャパン」にご来場ください。「フードテックジャパン」とは、食品製造に関する自動化技術やDXソリューションが一堂に出展する展示会です。IoT・AIソリューション、ロボット・FA機器、製造・検査装置をはじめとする、食品製造業のDXに関連する製品が出展します。
新技術の展示だけでなく、有力企業によるセミナーも併催される他、食品業界に関する最新の情報収集が可能です。事前登録すれば無料で入場可能なので、DXに興味がある方はぜひこの機会にご来場ください。
また、出展側としての参加も可能です。展示会には食品、飲料、製菓、健康食品など様々なメーカーの生産・製造、工場設備、経営部門の方々が来場します。自社製品のアピールの場や新たな市場開拓、関連企業と接点を持つ場として、ぜひご活用ください。
DX推進の必要性を感じているものの、必要なノウハウがない方や、自社に有効な製品を見つけたい方は来場を検討してみてはいかがでしょうか。
■ 第6回 フードテック ジャパン 東京
2025年12月3日(水)~5日(金)
■第4回フードテックジャパン大阪
2025年2月25日(火)〜27日(木)
食品製造業のDX推進は事業存続に関わる重要な要素
食品製造業には、少子高齢化に伴う人手不足や市場規模の縮小、品質管理水準の向上など様々な課題があり、全てを人力だけで解決するのは難しい状況です。DXは食品製造業の課題を解決する方法として期待されており、実際に導入している企業は約8割がその成果を実感しています。
一方、ノウハウや資金不足で導入に踏み切れない企業も少なくありません。DX推進は自社にとって現実的かつ効果的な業務に少しずつでも取り入れていくことが大切です。
食品製造業でDX推進に興味があるなら、ぜひ「フードテックジャパン」にご来場ください。IoT・AIソリューション、ロボット・FA機器、製造・検査装置などをはじめとする、食品製造業のDXに関連する製品が出展する展示会です。
来場側、出展側双方にメリットがあるので、ぜひこの機会にご来場ください。
▶監修:宮崎 政喜(みやざき まさき)
エムズファクトリー合同会社 代表 / 料理人兼フードコンサルタント
出身は岐阜県、10代続く農家のせがれとして生まれ、現在東京在住。プロの料理人であり食品加工のスペシャリスト。また中小企業への経営指導、食の専門家講師も務めるフードコンサルタントでもある。飲食店舗・加工施設の開業支援は200店舗以上。料理人としてはイタリアトスカーナ州2星店『ristorante DA CAINO』出身。昨今、市町村や各機関からの依頼にて道の駅やアンテナショップも数多く手掛ける。今まで開発してきた食品は1000品目を越え、商品企画、レシピ開発、製造指導、販路開拓まで支援を日々実施している。
▼この記事をSNSでシェアする